言友会の活動
偶然に会い、なんとなく別れてゆく淡白な出会いの多いなかで、その人と私の出会いは何かが起りそうな、そんな殺気をはらんでいた。
民間矯正所に籍を置き、「どもりが治るのならなんでもやってやろう」と意気盛んだった私は、「講談のリズムでどもりを治そう」との田辺一鶴さんの呼びかけにもすぐに応じていた。今でこそテレビ・寄席などで大活躍の一鶴さんも、トレードマークのヒゲがまだ生えやらぬほんのかけ出しだった。どもりを治すために講談の世界に入り、講談ではどもらなくなったという実績をふまえての呼びかけだけに、かなりの人が集まっていた。

1人での個人参加が多いなかで、ひときわ声高にしゃべる集団参加の一団があり、その声がそれでなくてもおとなしいまわりの人達をますますおとなしくさせていた。私が矯正所仲間を大勢ひきつれて顔をみせていたのだった。一応の説明が終った時、おとなしいはずの参加者のなかから異質な人間が前に出て、「先生」と、大声を出した。これまでの説明の間にはみかけなかった顔だった。医者と教師以外の「先生、先生」に不快感を持っている私には、それだけでいやになっていた。
「私もどもりを治すためのこのような会のできるのを待っていました。私も一生懸命やりますから頑張りましょう」と握手を求め、贈り物まで手渡した。説明も聞いていないで、私達大集団をさしおいての大きな態度に私達は相当頭にきていた。
矯正所仲間のなかで、どもることにかけては質量共に1番と折り紙つきのK君には、態度そのものより彼の口から飛び出す流暢な日本語にがまんならなかった。会合が終るとK君はその人に詰め寄っていた。「君は全然どもらないのになぜこの会に来たのか?それに贈り物なんかして何か魂胆でもあるのか」。仲間内では通じるK君のことばもその人には通じなかったかも知れない。しかし、K君の態度からただごとでないことはわかったらしかった。
一瞬殺気立った空気が流れ、帰りかけていた人も立ち止った。「なあ、みんなで食事でもしてゆっくり話そうや」と、声をかけたのは今は故人となられた親話会(どもり矯正会)の依田さんだった。冷静に考えれば彼に詰め寄る積極的な理由を見つけられなかった私達は、その言葉に救われた思いだった。むしろK君の森の石松ぶりにおかしさすら感じていた私達は、むろん全員参加でのぞんだ。
おなかが一杯になったK君がおとなしかったので話ははずんだ。「遅れて来たんで、すわる場所がなかったんです。それで『チョット』と思ったパチンコで、思いがけずにとれた景品を、持って帰るのもめんどうなので渡したのがどうも誤解されてしまって」と、その人はテレて説明をした。大笑いだった。誤解はとれてもK君にとっては、「私も前はひどいどもりで苦しんだんです」のことばだけは納得いかなかったらしい。それだけその人の日本語は確かなものだった。
この人こそ、言友会の生みの親、長い間東京言友会の会長をつとめ、全国言友会運動の先頭にも立つ丹野裕文その人だった。そして民間矯正所の仲間をひきつれてきていたお山の大将は、当時大学1年生の私で、言友会はこの2人の殺気だった出合いから始まったのだった。
矯正所で格闘するどもりたち
私には、丹野さんがどもるどもらないより、彼が歯学部の学生で家が歯科を開業していることの方に関心があった。私の歯はやぶ医者に徹底的に痛めつけられていたのだった。私はずうずうしくもさっそく丹野さんの家を今度は一人でたずねていた。これが丹野さんと私のつきあいの始まりである。
私の虫歯が治るころ、一鶴さんの「講談教室」への参加は随分減っていた。また依田さんの親話会も謡曲が中心で若者の心をとらえることはできなかった。
私の通っていた矯正所といえば、「ユックリ、呼吸を整えて話せば治る」というのが基本で、「わーたーくーしーはー」の、どこか間の抜けた話し方を守る者が優等生ということになっていた。早口でしゃべりまくる私など、基本に忠実でない劣等生であった。まじめな人間からは、「君は本当にどもりで悩んでるのか」とまじめに聞かれもした。
ここには北は北海道から南は沖縄まで全国各地のドモリストが集まり、社会人の多くが職を捨ててまできていた。中小企業で働く者に、1ヵ月間の吃音矯正のための東京行きは職を捨てることにも等しかった。よくなったと喜んで帰る人に、「あれは一時的なもので、すぐに元にもどるさ」と、3回目というS氏が先輩顔に話すのが印象的であった。でもみんな一生懸命に頑張っていたし、雰囲気も結構楽しいものであった。
劣等生の私には、いつの頃からかどもりの治る治らないより、どもりの人がこんなにもいて、それぞれ力いっぱい闘っているのだという現実に関心があった。私はどもりがこんなにも大勢いる、ということが大きなショックだったのだ。
吃音者の組織づくりを決心する
矯正所の有効期間も終り、講談にもあき始めていた私は、赤倉という学生と丹野さんを訪れていた。当時を振り返って丹野さんは、
「私は講談のリズムによる矯正法というよりも吃音者の会づくりに興味をもち、毎回出席していたが、その間多くの吃音者と知りあいになることができたのである。そしてその中の数名の人とともに親話会の会合に出席し、一鶴氏の講談教室と合併して新たな会を作っては、と提案したが予期に反して猛反対にあってしまった。私としても、以前吃音者の会づくりに失敗している経験があるので、新たな会づくりの意欲はなく、また一鶴氏の教室のように会員の減少を見るにつけても、吃音者の組織づくりの至難さがつくづくわかるのである。
そんなとき私の家へ、一鶴教室で知りあった赤倉智(日大生)、伊藤伸二(明大生)の2人が訪れ、是非とも自分たちで新しい会を作ろうと相談をもちかけてきた。
しかし、私としても以前の失敗があるので、即座に応ずるわけにはいかなかった。が彼等の情熱と若いエネルギーならばもしかしたら今度は成功するかも知れない、と思う気持ちもあった。そこで彼等に質問した。
『自分はやり出したからには最後までやり通したい。君達にもその意気込みがあるのか?』すると2人は口をそろえて『必ずやり通す。失敗しても最後まで頑張っていく』と熱意をこめて答えてくれたので、『それでは!』と会づくりをする決心をしたのである」。
(言友会誌『泪羅』7号より)
言友会結成
昭和40年10月、13名のサムライが上野公園に集まった。熱っぽい話し合いに、映画好きのA君は、「血判状を作って誓おう」とまで言い出した。彼こそ最初の脱落者だったのだから、血判状を作っておけばとくやまれる。会の名前をつけるのに相当の時間を必要とした。「わかば」「あすなろ」は紅一点のM子さん。政治好きのK君は、「日本吃音同志会」「吃音撲滅同盟」などといかめしい。50近くの名前が出て迷っていた時、それまで押し黙っていた神野芳雄君が重い口を開く、「ことばで結ばれる……ことばのとも……言友会」このことばで「言友会」は誕生した。
その後の役員人選では、丹野裕文会長、伊藤伸二幹事長以下、11名全員役員という豪華な体制を作りあげた。私達は一日も早く会員を集める必要があった。役員ばかりでは会は動くものではないのだ。
講談・詩吟・弁論・話し方・社交ダンスのクラブ活動中心の例会は厳しい中にも楽しさいっぱいで、役員の自覚で欠席者はほとんどなく、例会後の喫茶店の語らいがまた楽しく、私達は日曜日の例会が待ち遠しくてならなかった。私達にとって丹野さんはよき先生であり、また、兄貴でもあり、丹野さんの魅力が言友会の全てのような感じだった。それでも1ヵ月もすると、会員が増えていたのに例会参加者は減り、寒い冬の数名の例会はさびしさも一段とこたえた。早くもピンチを迎えたのだ。
翌41年1月中句、言友会の一大転機を迎えた。丹野さんの投書が朝日新聞に掲載されたのだった。言友会のマスコミ界への初陣であった。
◇サークルへの誘い◇
「現在、日本の吃音矯正はすべて民間に委託されているが、営利が目的で、真に吃音者のためを考えていないようです。それで都内に住む吃音者有志で言友会を作り吃りを吃音者自身の団結の力で克服しようと試みています。会員は現在30余人で、弁論、講談などのクラブ活動を行っています。吃音者の参加を歓迎します」。
反響はすごく、電話や手紙で問い合わせが殺到し、言友会は役員だけの会からの脱皮に成功した。毎週水曜日開かれていた幹事会に新しい人も加わり、熱っぽい話し合いが続いた。終わったあとのおにぎり屋での一杯こそ若い私達をひきつけていた。会の将来を、また先輩の人生をみんなで考え語るうちによく最終電車に乗り遅れ、近くの会員の家で泊ったりもした。丹野さんのエネルギッシュな言動が会に熱っぽい雰囲気を与え、人間関係も血の通ったものになったり、会は除々に力をつけてきた。
言友会発会式
昭和41年4月3日、朝日新聞は大スクープをやってのけた。他紙に全く載っていない大きな記事。「力を合わせてどもり克服に励む言友会、今日発会式」3段抜きの大きな扱いに、私たちの2ヵ月にわたる努力がむくわれた思いだった。例会にほとんどの会員が参加し、演劇に講談にと練習にはげんでいたのだった。新聞を見ると私はすぐに丹野さんの家に向った。
2人で会場に向う車のなかで私達ははしゃいでいた。「あんなに大きく出たんだから200人は来るな」「いや300はかたいよ」やけに車が遅かった。みんなもすでに新聞のことを知っていてうれしそうに準備をしていた。記者席、来賓席は前列に用意した。私といえば300人の大聴衆の前での報告を頭にえがいて胸は高なっていた。しかし開始の時間が来ても目につくのは準備をしている会員だけ、30分遅らせても結果は同じで、会員すら全員参加でなく、新聞を見てきた人などほとんどいなかった。
私たちはここでやっと現実に戻らなければならなかった。やたらと主のない椅子席が目立ち、私はそこに目をやりながらこれまでの会の報告をした。どもる元気もなかった。でも、会員は出席者の少ないのに反発するかのような熱演ぶりだった。中でも演劇部の「模擬国会」の迷演には、笑いとひやかしの声援がとんだ。みんな素直に自分の地を出していたのだ。
老朽した家屋を事務所に
発会式が無事に終って、会員も80名近くになり、いろいろな活動が可能になってきた。新聞発行、会員の連絡と会の仕事は急に増え、いつまでも丹野さんの家をずうずうしく使うわけにはいかなかった。聞きとりにくい電話、それもひんぱんにかかってきては丹野さん一家がノイローゼになるのも無理なかった。
しかし役員以外の会員はどこまでもずうずうしく、総会で提案された「事務所設置のための“千円カンパ”に猛烈に反対をし、そのまま丹野さんの家を使っていこうと言うのだった。やっとの思いで、わずかの差で可決されたものの前途は暗かった。
そんなとき私達の新聞での呼びかけに、すぐ応じてくれたのは、かつてどもりで苦しんだ板谷松栄さんで、その日すぐ私達は喜びいさんで坂谷さんの貸そうという一軒家に出かけた。港区白金とくれば迎賓館が頭にうかぶ東京の一等地、この家がその家ですと言われてもしばらく信じられなかった。東京の文化財保存の実績を誇るかのように、今どきめずらしい汲み取り式の便所までついていた。私達が靴をぬいで上ろうとすると、そのままでいい、とおっしゃる。恐る恐る足を踏み入れると、“バリ!”と床板が破れる。私はもうがまんならなかった。とても人が住めるとは思えなかったのだ。案の定10年近く人が住んでいなかったらしい。
若い私達の思いは通じず、板谷さんと丹野さんの話はすすみ、1ヵ月5,000円で話は決った。総会でもめながらも集めたカンパ金は全て家屋修復に使われ、会員である大工さんを中心に10数名の会員が作業にあたった。ほこりにまみれているうちに、私達はこのボロ家に愛情をいだき始めていた。電話が入りタタミを入れ替えると泊り込む人も増え、まさに仲間のたまり場となっていった。
治す努力の否定
事務所が言友会の活動の中心の場となるにつれ、そこには常に明るい笑い声が絶えなかった。若い私たちには雨もりのするどんなボロ屋でも、5人も10人も同じ屋根の下で夜遅くまで語れる場があるということはありがたかった。マージャン屋や酒場に早替わりすることもたびたびあったが、悲しいときうれしいとき、自然と足は事務所に向かった。
会が充実するにしたがって、これまでの活動では物足りなくなってきた私たちは、何か夢のあることがしたくなっていた。また言友会の存在を大きくアピールすることはできないか、常にそのことが頭の中にあった時期でもあった。
ある日、新聞で「若者たち」という映画が制作されながら、配給ルートが決まらず、おくらになりかけているという記事を読んだ。テレビで放映されていたものが映画化されたのだった。テレビで感動を受けていた私は、いい映画が興業価値がないことでおくらになることが不満だった。そしてその置かれた立場を言友会となぜかダブらせていた。

「そうだ、この映画を全国に先がけて言友会で上映しよう。そして吃音の専門家に講演をお願いし、講演と映画の夕べを開こう。吃音の問題を考えると同時に、映画を通して若者の生き方を考えよう」
そのことが頭にひらめくと私の胸は高鳴り、もうじっとしておれなくなった。さっそく制作した担当者に電話をし、新星映画社と俳優座へと出かけていった。どもりながら前向きに生きようとしている吃音者のこと、言友会のこと、そして今の私たちに必要なのは、映画『若者たち』の主人公のように、社会の矛盾を感じながらも、社会にたくましくはばたこうとする若者の生き方であることを訴えた。私たちの運動には理解や共感をしえても、末封切の映画の無料貸し出しとは別問題であった。あっさりと断わられたが、私は後ろへ引き下がれなかった。東京の吃音者に言友会の存在を広く知らせ、共に吃音問題を考え、生きる勇気を持つにはこの企画しかないと私は思いつめていたのだ。
私は、六本木にある俳優座にその後も何度も足を運んだ。交渉を開始してすでに7ヵ月が過ぎた。そして、映画『若者たち』も上映ルートが決まらぬままであった。再度私はプロデューサーに長い長い手紙を書いた。あまりのしつこさにあきらめたのか、情勢が変化したからなのかわからなかったが、この手紙がきっかけとなって映画を無料で借り出すことに成功した。そして、上映運動が展開される時には協力を惜しまないことを約束した。これまで私が生きてきてこの日ほどうれしかった日はかつてなかった。さっそく事務所にいる仲間に伝え、手をとりあって喜んだ。
とにかく、250名もの人を集め、主演の山本圭も参加してくれての夕べは成功した。会場を出る時参加者は『若者たち』の歌を口ずさんでいた。
吃音者、街に出る
私たちのすばらしいオンボロ事務所も、4年間の会の活動の重みに耐えられなくなるほどに老朽化してきた。これまで活動が続けられたのはこの事務所のおかげと思えば、壊れてしまうのをそのまま見過ごすわけにはいかなかった。
会費月200円の言友会に、事務所を修理するまとまったお金があるわけではなかったが、私は昭和45年の活動方針に事務所改築を入れた。方針案説明の時その費用の捻出方法を質問された私は、何とも答えられなかった。
故吉田昌平氏と私は、京都と東京に離れてはいたものの、会活動で困ったことが起きた時や新しいことを考えついた時、私が京都へ出かけたり、彼が東京へ来るなどして常に密接に連絡をとりあっていた。新宿のサウナが彼と私の会議室だった。ゆったりした休憩室の中に2人でいると、夢はいつも果てしなく広がっていくのだった。私以上に政治の力を信じ、政治活動にもエネルギーを集中してきた彼は、私に吃音問題の解決のための請願運動の必要性を説いた。賛成をした私は、それでは全国的な規模でカンパ運動にもとりくもうと逆に提案をした。若かった私は恥ずかしいことに、その時カンパ金の方により強く心 が動かされたのだった。
さっそく東京、京都、その他の言友会で話しあいがもたれ、署名、請願運動を全国の言友会が展開することになった。署名用紙やビラが印刷され、狭い事務所がより狭く感じられるほど積み上げられた。「これだけのビラを配るのに1年はかかるぞ」とそそっかしい印刷担当者を責めたが、あとのまつりであった。
事務所で泊ることの多かった私は、いつも山と積まれたビラを眺めながら眠りについた。このビラを早く片付けなければならない。私たちは請願運動にエネルギーを集中していった。立看板が用意され、ハンドマイクがあるメーカーから提供された。それらを運ぶトラックも用意された。署名カンパ運動が始まったのは、冷たい風の吹きつける2月のことであった。
「ご通行中の皆さん、私たちはどもりです。自分のどもりを克服しようと集まっている言友会の者です。言語障害児対策は日本ではたいへん遅れています。
全国にもっともっと多くの言語治療教室の設置と専門の治療機関を作らねばなりません」時にはどもり、時には大雄弁家になったつもりでマイクを手にした。新しく入った会員も古い会員も街頭に立った。

1週間に3日、今日は有楽町、明日は目黒と東京中で署名カンパ運動が続けられた。昭和45年2月から12月の11ヵ月の間に、署名約5千、カンパ金43万円、言友会の会員の個人カンパを含めて60数万円が私たちの手元に集まった。
事務所新築に動く
その頃、言友会には、責任ある活動をしていくための専従がおかれた。その費用は全てカンパに頼らなければならなかった。60数名が毎月会費の他に500~1,000円のカンパを継続してくれることになった。ともすれば全ての仕事を引きうけがちになり、昼間は一人きりで事務所にいる専従者を孤立させないためにも私たちは力を入れて活動を続けなければならなかった。その熱意が実ったのか、その年の言友会の夏の合宿には103名という記録的な参加者を得た。吃音者のエネルギーが千葉の海に爆発したのだった。
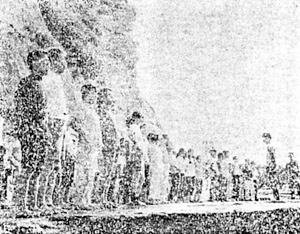
しかし、事務所改築の交渉は順調には進まなかった。「新しく建てた建物は板谷氏の登記とするかわり、半永久的に言友会が使用し、家賃の月5,000円は20年間据え置く」という条件に、運営委員会では議論が百出した。言友会が全額費用を負担し、更に家賃を払うのはおかしいという意見が強く出され、たびたび板谷氏と交渉を重ねた結果、時価250万円する借地権を70万円で買い取ることに成功した。寒い夜、凍える手でマイクを持って訴え、寄せられた暖かいカンパ金60数万円は全て借地権の買い取りで消えた。常識では考えられない安い買い物ではあったが、お金のない言友会にとっては大きな金額であった。事務所新築は新しい局面を迎えた。
全障研とともに事務所を
障害者運動に積極的に関わる中で、私たちと全国障害者問題研究会(全障研)とのつきあいが始まっていた。
そんなある日、私は、新宿にある全障研の事務所に遊びに出かけた。6畳一間のアパートを事務所として使用していた全障研も、また事務所を求めていることをそのとき知った。世間話の中から、言友会が事務所を作ろうとしているとの話がでた。そして共同出資で事務所を建てようというところまで話が進んだ。

建築費用は折半し、所有は言友会で、5年間無料で全障研が1室を事務所として使い、5年たった時点で全障研が出した金の半分を返却するという条件は、私たち言友会にとっては願ってもないことであった。しかし、借地権買い取りその他ですでに80万円近いお金を使いきり、私たちにはお金が全くなくなってしまっていた。私たちはまた金策に苦労しなければならなくなった。
その年5月の第4回言友会全国大会(名古屋)では、事務所新築を東京言友会のものと考えず、全言連の事務所として位置づけ、全国でカンパ運動に取りくむという大会決定がなされた。
全国の仲間に励まされ、私たちはまた活動を開始した。私たちは再び街頭へ出るとともに、全会員にさらにカンパを要請した。
カンパとともに、自分たちの力で少しでもお金を稼ごうと建築を請け負ってくれた建築会社でのアルバイトが始まった。毎週日曜日私たちは朝8時に集合した。建築資材の整備が私たちの仕事であった。炎天下まっ黒に日焼けした私たちは上半身裸で作業に励んだ。交通費は自己負担、さらにそこで得た報酬は全て事務所建設の費用になるという条件の中でも多くの人が参加をしてくれた。働いている人にとっては日曜日は休息日、それを返上しての参加だった。近くを通りかかったからと西瓜の差し入れをしてくれた会員、また建設会社の人の善意に励まされながら、私たちは汗にまみれた。
「風呂代ぐらいは出そう」と言うと、「風呂代、出してくれるのですか?」と若い会員がうれしそうに言った。その頃の風呂代はまだ50円だったであろうか。みんなと汗を流しあい、風呂につかりながら、一日の仕事ぶりを話しあった。
「今日の分はトイレのタイル分ぐらいかな」
私たちは、新しく建つであろう建物に思いをはせた。このバイトは、事務所が新築されてからも続いた。言友会のエネルギーが一気に爆発した頃の活動は楽しかった。事務所には常に5、6名が泊まりこみ、記念祭に、文化祭に、合宿にと言友会三大行事に取りくんだ。事務所新築が決まり建設会社との契約をかわした私たちは、次の目標、5周年記念大会へとエネルギーを集中させた。
映画『若者たち』のスタッフを囲んでの討論会、みんなで歌う歌「言友会の歌」の発表、夢のような企画が会員のしゃにむな活動によって現実のものとなっていった。
言友会の歌は、「若者たち」「昭和ブルース」の作曲家、佐藤勝氏が心よく作曲を引きうけてくださった。言友会の歌がテープによって届けられたとき、事務所で仕事をすませたあと、みんなで何度も何度も聞いた。さっそく生演奏のあるビアホールに楽符を持っていき、演奏してもらった。お客さんはどもりの人たちの歌とも知らず、私たちの歌に手拍子を打った。愉快だった。
当日は、いろんなサークル、障害者団体の人びとがかけつけてくれ、400名の人が言友会の創立5周年を祝ってくれた。その数日後に旧事務所の取り壊しがあった。
いろいろな活動があった。けんかをしたり飲んだりした。失恋に泣きむせんだ人もいた。ボロ屋だけど本当にみんなが親しんだ事務所が今取り壊される。私たちの思いを知る由もない建設会社の人たちが無造作に取り壊していく。「もっと大事に扱ってください。」
10名ほどの会員の見守る中、事務所は音をたてて崩れていった。涙が一筋、ほおを伝った。ありがとう。長い間ありがとう。
私たちは心の中で叫んでいた。

故吉田昌平氏の思い出
私が言友会の活動の中で涙を流したのは、旧事務所が取り壊される時と吉田昌平氏の死に直面した時の2回である。
言友会が好きで好きでたまらなかった彼と私はまさに言友会の虫であった。言友会の大会の議事の最中に喧嘩をしたり、意見が合わないと言っては何度も喧嘩をした。「お前みたいな奴とはもう会いたくない」とお互いに何度この言葉を言い合っただろうか。それでも私たちは離れることはなかった。彼は私にとって本気で怒りをぶつけられる相手であった。
彼との出会いは昭和41年7月の下旬であったろうか。久しぶりに事務所を訪れた私は、見かけない男が一人、自分の家のように住みついているのを見て驚いた。一見おとなしそうで、変に図々しいこの男の間の抜けたけた話しぶりが、この家にいることの正当性を主張していた。
話してみると愉快な男で、自分が何故ここに住んでいるのかを、おもしろおかしく語ってくれた。どもりに悩み、なんとかどもりを治したいと思いつめた彼は、職を捨て、恋人と離れて東京のどもり矯正所に来たのだった。そこで言友会を知り、例会に参加するうちに会がおもしろくなり、京都にも言友会を作ろうと決意したという。
ちょうど夏休みに入っていた私は、彼と私と、そしてSとIとの4人で共同生活を始めた。彼が土方やダンプの運転手をして稼いだお金は、私たちの夕食代に消えていった。カレーライスやブタ汁を作り、夜も遅くまで語り明かした。2ヵ月にわたる私たちとの付き合いの中で、彼は京都で言友会を作るエネルギーを貯えていった。
彼は、その後京都に戻り、言友会を作る活動を開始した。9月下旬京都に帰り翌年の6月まで、職につかずに彼は言友会の専従として仲間作りや事務所作りに専念した。
活動家が育ち、会が軌道に乗ったのを見届けて、彼はタクシーの運転手になった。どもりながらも親切に応待する彼のタクシーは評判であったが、その料金収入のカーブは言友会の活動に対する貢献度と見事に反比例し続けた。
その後、京都ろうあセンターの職員になった彼は、水を得た魚のように手話通訳や聴力検査・聴能訓練に打ち込んでいった。彼の豪放でユーモラスな性格と、人並み外れた行動力は、ろうあ者と吃音者との結びつきに大きな役割を果した。彼のシンボルとも言うべき大柄な体と太い手の指で、体ごと語る彼の手話はろうあ者の信頼を得ていった。「僕は手話をやりながら話すとどもらない、君も手話をやったらどうだ」と私たちにも推めたものだ。
彼は京都、私は東京と生活の場は離れたが、二人は良く会った。彼は、私のことを「千三つ」と言っては良くからかった。大風呂敷を広げた話ばかりで、千に三つしかまともなことを言わないと皮肉るのだ。その彼とて、私に勝るとも劣らず話が大きかった。私たち二人が会うと夢は大きく広がった。
彼は、良く東京に出てきては私と新宿のサウナで話し合った。私たちは、それをサウナ会談と名付けた。京都では受け入れてもらえない話でも、東京では受け入れられて話が進んでいく。それに力を得ては、彼は「東京は実行することを決意し動き始めた」と京都の会員を説得し、強引とも言えるやり方で京都言友会をリードして行った。
その現われが、雑誌『ことばのりずむ』の発行であり第1回吃音問題研究集会の開催であった。
当時、全国に言友会が広がりつつある情勢の中で、彼と私は「吃音児・者の指導はいかにあるべきか」「各地で吃音に対してどのような取り組みがなされているのか」「吃音とは何か」などを全国のレベルで総合的に考える雑誌や研究会の必要性を感じていた。京都と東京が一体となって雑誌作りが進められ、昭和46年9月『ことばのりずむ』が創刊された。その後、彼が病に倒れるまで彼を編集責任者とする京都言友会がその発刊の責任を担っていった。
昭和47年5月には、彼を実行委員長とした第1回吃音問題研究集会が京都で開かれた。彼なくしてはとても開かれなかったと言われる集会であった。冒頭の「ハヒフヘ本日は……」で始まった実行委員長の挨拶は、未だに参加者の心に残っている。思えば、この吃音問題研究集会が終った頃から彼は時々頭痛を訴えるようになっていた。
正月には一緒にマージャンをやろうと言っていた彼が、卓を囲む直前の昭和47年12月29日、病に倒れた。すぐ京都の病院に駆けつけた私は、大きな体の彼が小さくなってベッドに横たわっている姿を見て胸が締めつけられた。「伊藤やで」と言った私の声に頭だけを動かしてわかったという合い図をしてくれた。
その後、一進一退を続けた彼だが、時には見違える程元気な時もあった。そんなある時、彼は私にこう言った。「なあ伊藤、この春大阪教育大学を卒業したら東京へ帰るやろ。オレも病気が治ったら家族みんなを連れて一緒に東京へ行くわ。二人で東京言友会の専従をしたら東京で大きな事ができるで。やはり東京は日本の中心や、東京で活動しなきゃなあ。早く治りたいわ……」
彼は病の中でも常に言友会のことを考えていた。その彼が、突然、余りにも急に昭和48年3月29日、帰らぬ人となった。病名は脳腫瘍であった。私の胸の中で、彼は今も生き続けている。「言友会を頼むよ」、彼はニッコリ笑ってそう言っているようだ。
1976年 伊藤伸二編著 『吃音者宣言』 たいまつ社 より
