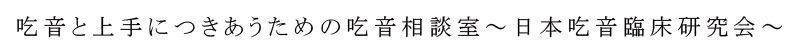第33回吃音親子サマーキャンプ 荒神山自然の家との打ち合わせ
第33回吃音親子サマーキャンプの参加申し込みが届き始めました。参加費も、郵便振替で届いています。また、サマーキャンプの中で子どもたちと取り組むお芝居をスタッフが練習する事前レッスンも近づいてきました。そんな中、先日、会 […]
文章を綴るということ
「スタタリング・ナウ」2006.2.25 NO.138 の巻頭言を紹介しようと読み始めて、ドキッとしました。遅れに遅れた年報の編集をしているとの書き出しに、今と全く同じだと思ったのです。僕は、今、毎月のニュースレター「 […]
第7回島根スタタリングフォーラム 親の話し合い 3
昨日の続きです。保護者との話し合いの時間が2日間で6時間もあったとはいえ、本当にたくさんのことを話していることにびっくりします。島根スタタリングフォーラムに参加し、そこで、同じようにどもる子どもや保護者に出会い、お互い […]
第7回島根スタタリングフォーラム 親の話し合い 2
昨日のつづきです。読み返してみると、子どもは参加せず、親だけが参加というところもあるようです。僕たちの主催する吃音親子サマーキャンプでも、どうしても子どもが行きたくないと言うので親だけが参加したことがありました。真剣に […]
第7回島根スタタリングフォーラム 親の話し合い
「スタタリング・ナウ」2006.1.21 NO.137 で特集している第7回島根スタタリングフォーラムでの、親の話し合いの記録を、今、読み返してみて、吃音を切り口に、なんとも幅広く、そして深く、考えて、その考えをことば […]
報道の魂~番組に込めたもの、番組を観た人の感想~
今日は、6月30日。今年の半分が終わろうとしています。時間が経つのが、怖ろしく早いです。7月には、親、教師、言語聴覚士のための吃音講習会、8月には、吃音親子サマーキャンプと続きます。どちらも、参加申し込みが届き始めまし […]
斉藤道雄さんとの出会いのきっかけとなった、《「弱さ」を社会にひらく》
斉藤道雄さんとの、奇跡のような、不思議な出会いとなった、僕の記事を紹介します。 大阪市内に、應典院(おうてんいん)というお寺があります。「ひとが集まる。いのち、弾ける。呼吸するお寺」が、應典院のキャッチフレーズでした。 […]
斉藤道雄さんの『メッセージ』
2005年、斉藤道雄さんから送られてきた原稿を読んで、僕が涙が止まりませんでした。そして今、その原稿を読み返して、また涙が滲んできます。 僕は、不思議な出会いをたくさん経験してきていますが、斉藤さんとの出会いもまたとて […]